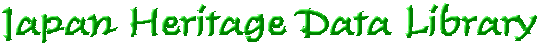
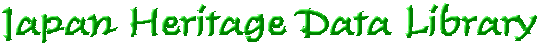
| 市町村 | 名称 | 概要 | |
| 北海道 | ***** | オホーツク海の流氷 | 1月〜3月、流氷のせめぎあう音が「キュー」「グー」と聞こえてくる |
| 札幌市 | 時計台の鐘 | 札幌農学校演武場として建設。百年以上の間、鐘の音を響かせる | |
| 函館市 | 函館ハリストス正教会の鐘 | 教会の鐘楼の6個の鐘が、毎週日曜日の10時に鳴り響く | |
| 東川町 | 大雪山旭岳の山の生き物 | 旭岳ではナキウサギ、コマドリ、ミソサザイなど多くの動物の声がする | |
| 鶴居村 | 鶴居のタンチョウサンクチュアリ | 多い時には200羽を越す鶴が集まる。つがいが鳴き合う声、若鳥の声 | |
| 青森 | 八戸市 | 八戸港・蕪島のウミネコ | ウミネコの「ミャー、ミャー」という鳴き声は、漁業の町の音風景 |
| 三沢市 | 小川原湖畔の野鳥 | 初夏、珍しいオオセッカを始め、コジュリン、コヨシキリ等がさえずる | |
| 十和田湖町 | 奥入瀬の渓流 | 十和田湖畔の子ノ口から焼け山に至る、14kmの渓流のせせらぎ | |
| 青森市など | ねぶた祭・ねぷたまつり | 「ラッセラー、ラッセラー」、「ヤーヤドー」という勇壮な掛け声 | |
| 岩手 | 大船渡市 | 碁石海岸・雷岩 | リアス式海岸で、洞穴に波が押し寄せ、雷鳴のような海鳴りが起きる |
| 水沢市 | 水沢駅の南部風鈴 | 毎夏、駅構内で爽やかな音色を奏でる。南部鉄器の町の風物詩 | |
| 滝沢村 | チャグチャグ馬コの鈴の音 | 6月に鈴を着けた百頭余りの馬が、お参り後、チャグチャグと行進する | |
| 宮城 | 仙台市 | 宮城野のスズムシ | 秋の夜、岩切城跡の茂み、与兵衛沼の周辺では鳴き声がよく聞こえる |
| 仙台市 | 広瀬川のカジカガエルと野鳥 | 夏ににカジカガエル、年間を通じセキレイ、カワセミなど鳥の声 | |
| 北上町 | 北上川河口のヨシ原 | 初夏から初冬にかけて、河面を渡る風がヨシのすれ合う音を誘う | |
| 築館町など | 伊豆沼・内沼のマガン | 毎冬やってくるマガンが日の出とともに一斉に飛び立つ羽音と鳴き声 | |
| 能代市 | 風の松原 | 松原を吹き抜ける風の音“松籟”が四季折々に楽しめる | |
| 山形 | 山形市 | 山寺の蝉 | 芭蕉の名句「閑さや岩に染みいる蝉の声」の舞台 |
| 鶴岡市 | 松の勧進の法螺貝 | 毎年12月、山伏たちがほら貝の音を響かせ、各家庭をまわり歩く | |
| 酒田市 | 最上川河口の白鳥 | 毎年10月に飛来する白鳥の求愛や飛行の時などのいろいろな鳴き声 | |
| 福島 | 福島市 | 福島市小鳥の森 | 福島市街地近くにある小鳥の森は、年間を通じて野鳥の声が楽しめる |
| 下郷町 | 大内宿の自然用水 | 江戸時代から使われる旧会津西街道の両脇を流れる用水路の水の音 | |
| 昭和村 | からむし織のはた音 | カラカラ、トントンという機織りの音が、古代布「からむし織」の里に響く | |
| 茨城 | 北茨城市 | 五浦海岸の波音 | 波の浸食で複雑に削り取られた崖・岩礁から太平洋の荒波が聞こえる |
| 栃木 | 栃木市 | 太平山あじさい坂の雨蛙 | 梅雨の頃、参道沿いに紫陽花が咲き、雨のしたたる坂で蛙が鳴く |
| 群馬 | 吉井町 | 水琴亭の水琴窟 | 手を洗った水が穴から水滴となって落ちると絶妙な音が聞こえる |
| 埼玉 | 川越市 | 川越の時の鐘 | 高くそびえる鐘楼から、毎日6時、12時、15時と18時に時を告げる |
| 江南町 | 荒川・押切の虫の声 | 初秋、日暮頃からマツムシ、スズムシ等が一斉に鳴き出す | |
| 千葉 | 佐原市 | 樋橋の落水 | 伊能忠敬旧宅内の用水路から水を落とす樋橋を復元したもの |
| 大多喜町 | 麻綿原のヒメハルゼミ | 数匹が鳴き始めると、一斉にジャージャーと鳴き、一斉に止む | |
| 千葉・東京 | 松戸市など | 柴又帝釈天界隈と矢切の渡し | 柴又帝釈天界隈は、昔ながらの商店や参拝客の賑わいがある |
| 東京 | 台東区 | 上野のお山の時の鐘 | 「花の雲、鐘は上野か浅草か」と詠まれた、上野寛永寺から響いた鐘 |
| 練馬区 | 三宝寺池の鳥と水と樹々の音 | 石神井公園にあり、水鳥の羽音・風に揺れる樹々のざわめきが聞こえる | |
| 武蔵野市 | 成蹊学園ケヤキ並木 | 春の新緑の葉ずれ、秋の落ち葉の音など、四季折々の音を奏でる | |
| 神奈川 | 横浜市 | 横浜港新年を迎える船の汽笛 | 大晦日の除夜の鐘の代わりに、世界に向かって一斉に鳴らされる汽笛 |
| 川崎市 | 川崎大師の参道 | 大師の参道での、「トントコ、トントコ」と調子をとりながら飴を切る音 | |
| 相模原市 | 道保川公園のせせらぎと野鳥の声 | 相模川の支流に整備された公園のせせらぎとメジロなどのさえずり | |
| 山梨 | 足和田村 | 富士山麓・西湖畔の野鳥の森 | ヤマガラ、コガラ等の声。青木ヶ原ではホトトギス、ジュウイチ等の声 |
| 長野 | 長野市 | 善光寺の鐘 | 10時から16時までの時の鐘。“善光寺の鐘を聞いた杏はよく実る” |
| 岡谷市など | 塩嶺の小鳥のさえずり | 八ヶ岳等の山並眼下の諏訪湖を眺めながら、野鳥の声を楽しめる | |
| 諏訪市など | 八島湿原の蛙鳴 | シュレーゲルアオガエル、ヤマアカガエル貴重なカエルの生息地 | |
| 新潟 | 豊栄市 | 福島潟のヒシクイ | ヒシクイの最大の飛来地。冬期、群れで舞う姿と鳴き交わす声 |
| 能生町 | 尾山のヒメハルゼミ | 能生白山神社がある尾山では、7月頃ヒメハルゼミの大合唱が聞こえる | |
| 静岡 | 遠州灘 | 遠州灘の海鳴・波小僧 | 天気の変わり目にゴオー、ザアーなどと突然鳴り出してスッと止む海鳴 |
| 本川根町 | 大井川鉄道のSL | 南アルプス山麓の奥大井に、昔懐かしいSLの汽笛が響く | |
| 愛知 | 名古屋市 | 東山植物園の野鳥 | 丘陵を利用した植物園で、シジュウカラ、メジロなどの野鳥に出会える |
| 渥美町 | 伊良湖岬恋路ヶ浜の潮騒 | 藤村の詩「椰子の実」の舞台。春夏は雄大な、秋冬は優しい潮騒の音 | |
| 三重 | 鳥羽市など | 伊勢志摩の海女の磯笛 | 海に潜ってあわびを採る海女が水面にでた時に発する口笛に似た吐息 |
| 岐阜 | 美濃市 | 卯建の町の水琴窟 | 江戸時代の街並みの、「旧今井家住宅」の中庭に古くからある水琴窟 |
| 八幡町 | 吉田川の川遊び | 城下町の真ん中を流れる吉田川の清流では、子供たちが川遊びをする | |
| 岐阜市など | 長良川の鵜飼 | 5月から10月にかけての長良川の風物詩 | |
| 富山 | 立山町 | 称名滝 | 滝の音が「南無阿弥陀仏・・・」と称名念仏を唱えているように聞こえた |
| 八尾町 | エンナカの水音とおわら風の盆 | 坂道に沿って流れる水路の水音。「おわら風の盆」時は聞こえない | |
| 井波町 | 井波の木彫りの音 | 早朝からトントン、コツコツと木槌を打つ音、ノミで木を刻む音が聞こえる | |
| 石川 | 金沢市 | 本多の森の蝉時雨 | 夏の朝と夕、森から降り注ぐヒグラシの蝉時雨は、清涼感を醸し出す |
| 金沢市 | 寺町寺院群の鐘 | 寺町は寺が多い。朝方や夕方、どこからともなく鐘の音が聞こえてくる | |
| 福井 | 武生市 | 蓑脇の時水 | 大平山の谷間の間欠冷泉。60分間隔で水が湧き出し、滝に落ちる |
| 滋賀 | 大津市 | 三井の晩鐘 | 近江八景の一つの音風景。毎夕5時頃、美しい鐘の音が時を告げる |
| 彦根市 | 彦根城の時報鐘と虫の音 | 時報鐘は、3時間毎に時を告げる。夏の夕暮れには蝉時雨が聞こえる | |
| 京都 | 京都市 | 京の竹林 | 嵯峨野・洛西の竹林が風にそよぎ、様々な音色で聞こえる |
| 園部町 | るり渓 | 「鳴滝」の雷のような音、「双龍淵」の織機のような音など楽しめる | |
| 網野町 | 琴引浜の鳴き砂 | 代表的な鳴き砂の浜。足で擦るように歩くとキュッキュッという音がする | |
| 大阪 | 大阪市 | 淀川河川敷のマツムシ | 秋の夜、多くの虫の声が聞こえ、特にマツムシの澄んだ鳴き声が響く |
| 八尾市 | 常光寺境内の河内音頭 | 「河内音頭」は口説きの形式の盆踊り唄で、日本を代表する音頭 | |
| 兵庫 | 神戸市 | 垂水漁港のイカナゴ漁 | 無数のイカナゴのはねる音とカモメの声と漁船のエンジン音が聞こえる |
| 姫路市 | 灘のけんか祭りのだんじり太鼓 | 10月、松原八幡神社と御旅山で行われる祭り。太鼓の音が響きわたる | |
| 奈良 | 奈良市 | 春日野の鹿と諸寺の鐘 | 早朝の春日野の鹿寄せホルンの音。夕暮れの興福寺、東大寺の鐘 |
| 和歌山 | 橋本市 | 不動山の巨石で聞こえる紀ノ川 | 巨石の穴に耳をあてると聞こえる川のような不思議な音 |
| 那智勝浦町 | 那智の滝 | 熊野詣を象徴する滝の音 | |
| 鳥取 | 米子市 | 水鳥公園の渡り鳥 | 中海に面する公園で、越冬のため飛来するコハクチョウの姿と鳴き声 |
| 三朝町 | 三徳川のせせらぎとカジカガエル | せせらぎ音と相まった、カジカガエルの「カラカラカラ」と澄んだ鳴き声 | |
| 青谷町など | 因州和紙の紙すき | 「ちゃっぽんちゃっぽん」と何回も何回も揺り動かしながら紙をすき上げる | |
| 島根 | 仁摩町 | 琴ヶ浜海岸の鳴き砂 | 琴ヶ浜の砂浜を歩くと、「キュッキュッ」と美しく心地よい音がする |
| 岡山 | 北房町 | 諏訪洞・備中川のせせらぎと水車 | 諏訪洞から湧き出てる水は、備中川のせせらぎとなり、水車を動かす |
| 新庄村 | 新庄宿の小川 | 出雲街道の新庄宿で、桜並木のある道の両脇から聞こえる小川の音 | |
| 広島 | 広島市 | 広島の平和の鐘 | 平和記念公園で8月6日に鳴らされる鐘は、平和の願いを世界に伝える |
| 尾道市 | 千光寺驚音楼の鐘 | 「音に名高い千光寺の鐘は、一里聞こえて二里ひびく」と言われる | |
| 山口・島根 | 小郡町・津和野町間 | 山口線のSL | 1979年に復活した蒸気機関車の音。「ボオーッ」という懐かしい汽笛 |
| 徳島 | 鳴門市 | 鳴門の渦潮 | 鳴門海峡では潮の干満で無数の渦が生じる。雷のような大きな音 |
| 徳島市他 | 阿波踊り | 阿波踊りが近づくと、街角から三味線で奏でる「ぞめき」の音が聞こえる | |
| 香川 | 長尾町 | 大窪寺の鐘とお遍路さんの鈴 | 四国霊場第88番札所。お遍路さんの鈴と、心地よい鐘の音が鳴り響く |
| 満濃町 | 満濃池のゆるぬきとせせらぎ | 毎年6月中旬、田植えを前に池のゆる(取水栓)を抜く豊作祈願の儀式 | |
| 愛媛 | 松山市 | 道後温泉振鷺閣の刻太鼓 | 道後温泉の本館振鷺閣にある太鼓の音。朝・昼・夕に打ち鳴らされる |
| 高知 | 室戸市 | 室戸岬・御厨人窟の波音 | 室戸岬に押し寄せる波の音が、御厨人窟の洞内に響く |
| 福岡 | 福岡市 | 博多祗園山笠の舁き山笠 | 「オイサッオイサッ」のかけ声と勢い水の水しぶきなどが一体となる |
| 太宰府市 | 観世音寺の鐘 | 天智天皇の創建と伝えられる観世音寺の、日本最古の鐘の音 | |
| 福岡・山口 | 下関市など | 関門海峡の潮騒と汽笛 | 潮流が激しい瀬戸。源平の壇ノ浦の合戦などの歴史を彷彿とさせる |
| 佐賀 | 唐津市 | 唐津くんちの曳山囃子 | 曳山行列で、わだちのきしむ音と鉦や笛、太鼓の音、お囃子が聞こえる |
| 伊万里市 | 伊万里の焼物の音 | 陶石を砕く石臼の音、ろくろの廻る音など伊万里焼にまつわる様々な音 | |
| 長崎 | 長崎市 | 山王神社被爆の楠の木 | 被爆を記憶する楠は、今も葉ずれの音を奏で、木の下に人々が集まる |
| 熊本 | 矢部町 | 通潤橋の放水 | 嘉永年間にできた石造りの水路橋。空に弧をかきながら水が躍り出る |
| 五和町 | 五和の海のイルカ | 天草の五和の海は300頭のバンドウイルカがいる。船上から声が聞ける | |
| 大分 | 日田市 | 小鹿田皿山の唐臼 | 小鹿田焼は水力利用の唐臼で陶土をつく作業から始まる |
| 竹田市 | 岡城跡の松籟 | 滝廉太郎の「荒城の月」の舞台・岡城跡で松の老木を吹き渡る風の音 | |
| 宮崎 | 小林市 | 三之宮峡の櫓の轟 | 渓流が、落差7m余りで、巨石に囲まれた滝壺に落ちる音 |
| えびの市 | えびの高原の野生鹿 | 秋に雄鹿が雌鹿を呼ぶ「キーン、キーン」という鳴き声が暗闇に響く | |
| 鹿児島 | 出水市 | 出水のツル | ナベヅル、マナヅルの我が国最大の越冬地。多数のツルの鳴き交わす |
| 屋久町 | 千頭川の渓流とトロッコ | 屋久杉の山を流れ下る千頭川沿いに、森林軌道のトロッコが走る | |
| 沖縄 | 竹富町 | 後良川周辺の亜熱帯林の生き物 | アカショウビン、オオクイナ、ハラブチガエル等の亜熱帯の生き物の声 |
| 勝連町など | エイサー | 太鼓と三味線でエイサー唄を歌い、踊りながら家々をまわる伝統行事 | |
|
|
|||